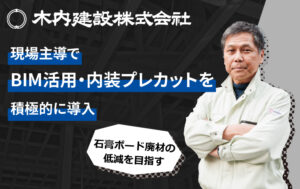内装職人が足りない!慢性的な人手不足が招く品質低下とは?
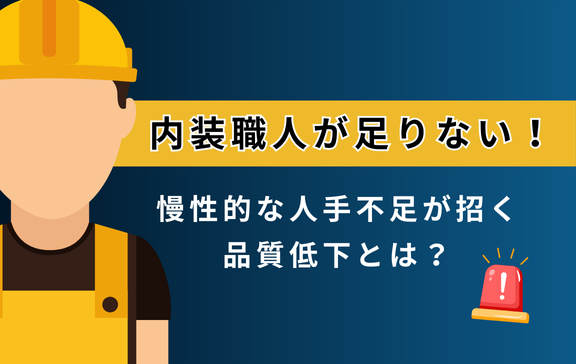
【目次】
どの現場でも起きている「人手が足りない」という共通課題
内装工事の現場では、職人が集まりにくい、いつもの協力業者が手配しづらい
──といった問題が顕在化しつつあります。
現場に従事される方であれば、「もう一人いれば今日中に終わるのに」「いつもの職人さんが来てくれれば安心なのに」と感じた経験をお持ちではないでしょうか。限られた人手で工程をやりくりする日常が、現場の疲弊感につながっています。
これまで当たり前だった「必要な時に、必要な人数の職人を確保する。」ことが困難になり、現場運営そのものに不安を感じる状況が続いています。特に内装工事では、仕上げの品質が建物全体の印象を大きく左右するため、経験豊富な職人の存在は欠かせません。しかし、その確保が年々厳しくなっているのが現実です。
人手不足は単に「人数が少ない」という表面的な問題ではありません。現在では多くの現場が直面する共通課題として、現場運営の根幹を揺るがす深刻なテーマとなっています。
人手不足を引き起こしている根本原因とは?
内装工事の人手不足は、単一の要因ではなく、複数の構造的な要因が重なって発生しています。
まず大きい要因は、ベテラン職人の高齢化と引退です。長年現場を支えてきた熟練工が次々と現場を離れる一方で、若手の新規参入は十分に進んでいません。建設業全体でも55歳以上の就業者が36.6%を占める一方、29歳以下はわずか11.6%にとどまっており【1】、世代交代がスムーズに進んでいない現状が浮き彫りになっています。
さらに、若手が定着しにくい環境も課題です。不規則な勤務時間や体力的な負担、「見て覚える」文化などが敬遠され、他業界へ流れるケースが後を絶ちません。待遇や将来性への不安も、この傾向に拍車をかけています。
また、協力業者ネットワークの縮小も見られます。地域を支えてきた工事店や職人グループのなかには、事業縮小や廃業を余儀なくされる例も見られます。
厚生労働省のデータによると、建設業で働く外国人労働者は約14万5千人(2023年10月時点)に達し、建設業界の労働力の一端を担っています【3】。ただし、言語や文化の違いによるコミュニケーション課題が残り、抜本的な解決には至っていないのが現状です。
このように、多様な要因が複雑に絡み合い、人手不足を慢性化させています。
現場に広がる「品質低下」と「納期遅延」の連鎖
人手不足は、現場の品質管理に影響を及ぼすことがあります。熟練工が不足した際には、経験の浅い職人に作業を任せるケースが増え、結果として施工や仕上がりにばらつきが生じる可能性が高まります。特に応援要員として急遽現場に入る職人の場合、初期不良や調整不足が発生しやすく、結果的に手直しや再施工が必要となるリスクが高まります。
さらに、人員に余裕がない現場では段取りや検査に十分な時間を割けず、不具合の早期発見が難しくなります。これが悪循環を生み出します。手直し作業が発生すると工程が遅れ、遅れを取り戻すためにさらに人手不足に拍車がかかり、品質チェックが後手に回るのです。
このような状況が続くと、工程遅延や顧客満足度の低下につながるリスクがあります。クレーム対応の負担が増すことで、現場所長の業務負担が増え、本来の管理業務に支障をきたす可能性もあります。人手不足が引き起こすこの連鎖を断ち切ることが、現場運営の急務となっています。
「見て覚える」文化の限界─内装工事特有の人材育成課題
内装工事には、人手不足をさらに深刻化させる特有の課題があります。属人化の壁が存在し、「〇〇さんにしかできない仕事」が現場に数多く残っているのです。納まりの判断、建材の選定、施工手順の決定など、経験豊富な職人の勘と判断に依存している部分が多く、技術やノウハウが体系化されにくい状況があります。
従来は「親方の背中を見て覚える」という文化が根付いてきましたが、現在の人手不足のなかではその余裕が失われています。ベテラン職人自身も多忙を極め、若手を一から指導する時間が取れない現場が増えています。さらに、工期短縮の要請が強まるなか、教育よりも即戦力を優先せざるを得ない傾向が続いています。
その結果、技能承継は進まず、ノウハウの体系化も遅れています。現場では日々の作業に追われ、標準化された手順書や教育プログラムの整備は後回しになりがちです。こうして優秀な職人が退職・引退すると同時に、貴重な知見が失われ、品質維持が困難になるという構造的な課題が生まれています。
一方で、省人化技術や働き方改革の取り組みも進みつつあり、現場環境の改善に向けた動きも広がっています。
現場でできる省人化と品質確保の両立策
人手不足のなかでも品質を維持するためには、仕組みによる解決が欠かせません。効果的なアプローチの一つが、作業や判断の見える化と標準化です。BIMなどのデジタル技術を活用することで、これまで職人の経験や勘に依存していた判断を、誰でも理解できる形に変換できます。材料の仕様や施工手順、品質基準を明確にすれば、経験の浅い職人でも一定水準の品質を維持できる環境が整います。
作業効率の改善も重要です。プレカット材の活用や建材手配業務の自動化を進めれば、現場での作業負荷を軽減し、限られた人数でも効率的に工事を進めることが可能です。
進捗管理の最適化も省人化に直結します。リアルタイムで工程を把握し、必要な箇所に適切なタイミングで人手を配置すれば、全体の生産性を高められます。
こうした取り組みを組み合わせることで、属人化を抑え、持続的に運営できる現場体制の実現が可能になります。仕組みによって「限られた人員でも高品質を守れる現場」をつくることが、これからの課題解決の核心といえるでしょう。
BuildAppが支援する「人手が足りない現場」の現実解
こうした課題に対応する実践的な解決策として、BuildApp 内装 建材数量・手配サービスがあります。
BuildApp 内装 建材数量・手配サービスの特長は、BIMモデルから建材の所要数量を自動算出し、発注から揚重・間配り計画までを一気通貫でサポートできる点です。これにより、ベテランの番頭・職長の頭の中にあった材料管理のノウハウを、誰でも扱える形式知として活用できるようになります。
現場での使いやすさにも配慮されており、複雑な操作を必要とせず、現場作業員が直感的に利用できる設計となっています。段階的な導入も可能で、まずは小規模な案件から利用を始め、徐々に適用範囲を広げることもできます。
BuildAppは、人手不足という現実的な制約のなかで「今ある人手で最大限の成果を上げられるよう支援することを目指しています」。属人化からの脱却と業務の標準化により、人が足りない現場でも品質を安定させやすい体制づくりの一助となることが期待できます【2】。
まとめ:人手不足でも品質を守るために必要な視点
内装工事における人手不足は、単に職人を増やせば解決する問題ではありません。属人化に依存した体制を見直し、現場全体を仕組みで支えることが求められています。
重要なのは、現場の「気づき」から改善を始めることです。まずは属人化した業務を洗い出し、標準化できる部分を特定することで、誰でも参加できる体制を整えられます。こうした取り組みを積み重ねることで、今いるメンバーで回せる持続的な現場運営が可能になります。
人手不足という課題に直面している今こそ、BuildAppなどの支援ツールを活用し、できることから始めることが重要です。小さな改善の積み重ねが、現場全体の生産性向上と品質確保につながります。

出典一覧
【1】クラフトバンク総研「2024年問題は「人手不足」の建設会社の経営にどう影響するのか? をデータできちんと検証する」
https://souken.craft-bank.com/analisys/tenshoku2024/
【2】BuildAppサービスサイト「【内装BIMの課題と展望】なぜ施工現場で止まるのか?──DX推進部門が直面する現場実装の壁とBuildApp 内装 建材数量・手配サービスの解決策」
https://build-app.jp/column/1504/
【3】厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37084.html