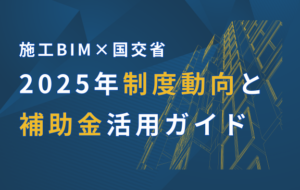設計施工一貫BIMの実務効果|分離発注との比較と導入メリット

BIM(Building Information Modeling)は建物情報を3Dモデルで一元管理する建設DXの中核技術ですが、その効果は発注方式によって大きく左右されます。特に近年注目を集める設計施工一貫方式は、多くの業界調査や事例でBIMとの親和性が高く、分離発注に比べて統合的なメリットが得られると報告されています。
本記事では、設計施工一貫方式におけるBIM活用の実務効果と分離発注との違いについて、具体的事例や最新動向を交えながら解説します。
【目次】
設計施工一貫方式とは?BIMとの親和性が高い理由
建設プロジェクトにおいて、設計と施工を別々に発注する「分離発注方式」が主流である一方、近年注目を集めているのが「設計施工一貫方式(Design-Build)」です。この方式では、発注者が設計と施工を一括で依頼するため、工程全体を通じた情報共有や責任の一元化が可能になります。
この設計施工一貫方式とBIMは高い親和性を持つとされています。理由の一つは、BIMが「設計・施工・維持管理の情報を一元化するプラットフォーム」であることにあります。従来の分離発注では、設計と施工の間に情報の断絶が生じやすく、BIMモデルの再構築や意図の伝達ミスといった非効率が発生していました。
一方、一貫方式であれば、初期設計段階から施工側のノウハウやコスト管理視点を反映したBIMモデル構築が可能となり、設計と施工の整合性が確保されやすい仕組みが整います。さらに、ECI(アーリー・コントラクター・インボルブメント)やCM(コンストラクション・マネジメント)方式などの発展型一貫方式では、早期から複数のステークホルダーがBIMを通じて空間・コスト・工程を検証し合うことで、意思決定の迅速化やトラブル回避といった副次的なメリットも実現されています。
BIMで変わる統合プロジェクト管理の実態
設計施工一貫方式とBIMの連携が進む中、プロジェクト管理の在り方にも大きな変化が生まれています。特に注目されているのが、CDE(Common Data Environment)と呼ばれる共通データ環境の活用です。これは、設計者・施工者・発注者などあらゆる関係者が、同一のクラウド上でBIMモデル・図面・スケジュール・チャット履歴などをリアルタイムで共有・管理できる仕組みです。
このような統合環境の導入により、会議や承認プロセスが大幅に効率化されています。従来、紙ベースやメールで行われていた情報共有は、CDE上でモデルを指し示しながら即時に判断・記録が可能となり、意思決定のスピードが向上しました。例えば、ある自治体の庁舎プロジェクト(延床面積約12,000㎡)におけるCDE+BIM活用事例では、移動時間削減や業務作業時間約2割削減が報告されています【1】。
さらに、設計段階で作成したBIMモデルが、そのまま施工・維持管理段階でも活用されることで、情報の断絶がなくなり、トータルでのプロジェクト品質と透明性が向上しています。遠隔監理や点検履歴の3D可視化といった応用も進んでおり、BIMは単なる設計支援ツールから、統合マネジメントの中核技術へと進化しているのです。
分離発注との比較で見えるBIMの導入効果
BIMの導入効果を評価する上で、分離発注方式と設計施工一貫方式(DB・ECI・CMなど)との比較は重要です。特に、効率性・コスト・品質の3つの観点からその違いを理解することは、プロジェクトの発注方式選定にも直結します。
効率性の違い
一貫方式では設計と施工が同一チーム内で連携するため、BIMモデルを起点とした情報共有がスムーズに行えます。CDE環境によりリアルタイムでモデルを確認・調整でき、意思決定の迅速化・手戻りの削減が顕著です。一方、分離発注では設計・施工間でBIMモデルの再作成やデータ引継ぎが必要となることもあり、情報の齟齬や非効率が発生しやすい構造です。
ただし、分離発注でも適切なBIM実行計画(BEP)や標準化されたIFC形式での情報引継ぎにより、情報連携の課題を軽減している事例も報告されています【2】。
コスト面での優位性
設計段階から施工性やコストを意識した設計が可能となる一貫方式が、結果的に変更・修正の削減につながり、総コストを抑制できる傾向があります。実際、あるCM方式プロジェクトでは、BIM導入により業務作業時間を20%以上削減し、見積修正や設計変更の頻度も低減した事例があります。
このように、多くの業界調査や事例から、設計と施工の連続性が確保された一貫方式の方がBIM活用に適しているとされ、とくに複雑な構造や長期的な維持管理が必要な中規模から大規模プロジェクト(延床面積5,000㎡以上、工事費10億円以上)で導入効果が報告されています【3】。
設計段階から施工・維持管理までのBIM情報連携
設計施工一貫方式におけるBIMの大きな強みは、設計段階で作成した3Dモデルの情報を、施工・維持管理フェーズまで一貫して活用できる点にあります。この情報連携は、国際標準であるIFC形式を用いたデータ共有や、プロジェクト進行に応じたLOD(詳細度)の設定によって実現されており、従来の2D図面主体のプロジェクトとは異なる効率的なワークフローを可能にしています。
具体的には、設計者が作成したBIMモデルを施工段階でそのまま活用することで、再入力や図面トレースといった非効率な作業が大幅に削減されます。さらに、すでに業界の一部企業では、BIMモデルを活用した干渉チェックや施工図作成の自動化を実現しており【4】、現在ではこうした取り組みが業界全体に広がりつつあります。その後も、施工段階で記録された情報を維持管理用に引き継ぐことで、FM(ファシリティマネジメント)やデジタルツイン活用の基盤として活かすことが可能です。
このような情報の連続性が実現することで、ライフサイクル全体を通じたコスト最適化や、意思決定の迅速化、品質維持といった効果が期待できます。特に、公共施設や大規模民間施設など、長期的な運用が求められる建物では、情報継承によるBIMの実務的価値がより一層高まっています。
大手ゼネコンにおける一貫BIM戦略の動向
設計施工一貫方式におけるBIM活用は、大手ゼネコン各社が先行して導入を進めており、社内のBIM専門部門やCDE(Common Data Environment)の標準運用など、プロジェクト横断での情報管理体制が着実に整備されています。特に、設計・施工・維持管理の各フェーズにおける情報継承を前提とした一貫したBIM運用ルールの策定が、社内ガイドラインとして明文化されるケースも増えています。
例えば、大手建設会社の一部プロジェクト(工事費50億円規模のオフィスビル)では、基本設計から施工図作成、竣工時の納品モデルまでIFC4.0形式で統一し、協力会社が共通環境でモデルを更新・確認できる仕組みを構築しています。さらに、設計変更の記録管理や施工中のモデル照合もCDE上で完結するため、日建連の一部事例では、関係者の作業時間が25から30%削減されたと報告されています【5】。
このような大手企業の取り組みは、中堅建設会社にも波及しつつあり、共通のBIMガイドラインや納品要件の整備が業界全体で進んでいます。今後は、発注者側との連携も含めた統合管理体制の高度化が求められる段階に入りつつあるといえるでしょう。
導入のポイントと今後の展望
段階的導入のポイント
設計施工一貫方式においてBIMを導入する際には、段階的な導入と社内体制の整備が成功の鍵となります。初期段階では、BIMを活用する領域やプロジェクトを限定し、小規模案件でのトライアルを通じて運用ルールやモデルの標準を確立する手法が推奨されます。また、CDEやIFCをはじめとしたオープンフォーマットへの対応など、技術的要件の整備と並行して、社内のBIM人材育成やガイドライン整備も重要とされています。
今後の業界動向
今後の展望としては、国土交通省が進めるBIM図面審査制度(詳細は国土交通省BIM推進会議資料参照)への対応が求められる見込みです【6】。また、AIやIoT、クラウド施工管理ツールとの統合によって、リアルタイムの施工管理や設備監視が可能な「スマート建設」への進化も視野に入ります。加えて、日本建設業連合会などによるBIM標準化ガイドラインの策定が進んでおり、業界全体での運用基盤の統一と、サプライチェーン全体でのデータ活用が期待されています。
ただし、導入に際しては適用条件の見極めが重要です。特に小規模プロジェクト(延床面積2,000㎡未満)や単純な構造の建物では、従来手法との費用対効果を慎重に検討する必要があります。
まとめ|設計施工一貫BIMの重要性
本記事で解説した設計施工一貫BIMの実務効果について、要点を以下にまとめます。
設計施工一貫BIMの主要メリット
- 設計と施工の情報が統合されやすく、効率性・コスト・品質の各面で高い効果を発揮
- CDEを活用した統合管理により、プロジェクト全体の意思決定スピードが向上
- 設計段階から施工・維持管理まで一貫した情報活用が可能
分離発注との比較結果
- 一貫方式:BIMモデルを起点とした円滑な情報共有により、迅速な意思決定と手戻り削減を実現
- 分離発注:適切なBIM実行計画があれば情報連携の課題は軽減可能だが、構造上の非効率は残存
- 導入効果は中規模から大規模プロジェクト(延床面積5,000㎡以上)で特に顕著
導入時の重要ポイント
- 段階的なアプローチと体制整備が成功の鍵
- 小規模案件でのトライアルによる運用ルール確立
- 技術要件整備と並行した人材育成
- ガイドラインの策定
- 小規模プロジェクトでは費用対効果の慎重な検討が必要
設計BIMは、設計意図の可視化や関係者間の合意形成に有効ですが、施工現場では、実際の作業に直結するより詳細な情報が求められます。
こうした内装工事における現場ニーズに応えるため、BuildApp 内装では、第一弾サービスとして「BuildApp 内装 建材数量・手配サービス」を提供しています。設計段階の情報をもとに、施工工程における建材手配を効率化します。

BuildAppでは、施工プロセスにおける業務・現場の「不」を解消するサービス・アプリケーションを提供しています。お気軽にご相談ください。
出典一覧
【1】国土交通省「第6回建築BIM推進会議」(2021年3月)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001395087.pdf
【2】一般社団法人日本建設業連合会「「BIM活用の実情把握に関するアンケートの実施報告」(2024年6月)
https://www.nikkenren.com/kenchiku/bim/seminar/pdf/report/2024/jfcc2024_d.pdf
【3】けんせつplaza「建築BIM推進会議における検討や建築BIMの推進に向けた取り組みの状況について」(2024年7月)
https://www.kensetsu-plaza.com/kiji/post/49238
【4】建設ITワールド「BIM活用によるリニューアル工事効率化事例」(2018年11月)
https://ken-it.world/success/2018/11/adsk-taisei-case.html
【5】一般社団法人 日本建設業連合会「施工BIMのスタイル事例集2024」(2024年6月)
https://www.nikkenren.com/kenchiku/bim/pdf/zuhan/bimstyle_2024.pdf
【6】建築確認におけるBIM活用推進協議会
https://www.kakunin-bim.org