施工BIM×国土交通省|2025年制度動向と補助金活用ガイド
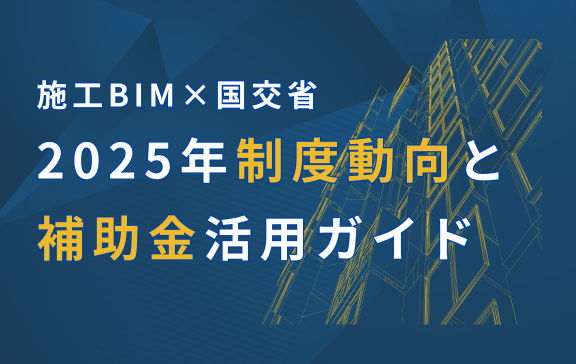
建設現場のデジタル化が急速に進む中、施工段階でのBIM活用(いわゆる施工BIM)が注目を集めています。施工BIMは、3Dモデルを活用した工程管理や干渉チェック、資材数量算出などにより、現場の生産性向上に寄与する技術として期待されています(※効果は現場や導入状況により異なります)。
本記事では、国土交通省が推進する政策や補助金制度の中から、特に施工フェーズで活用可能な支援施策に焦点を当て、現場実務の視点から体系的に解説します。
【目次】
国土交通省によるBIM/CIM原則適用の現状(2025年6月時点)
2023年度以降、国土交通省は一部の小規模工事や災害復旧工事などを除く多くの公共工事に対し、BIM/CIMの原則適用を進めています【1】。設計段階では3Dモデルによる空間検討、施工段階では干渉チェックや資材数量算出、維持管理では属性情報の活用といった取り組みが求められており、国土交通省直轄案件を中心に段階的な実装が進んでいます。
また、監督検査のデジタル化も進行中です【2】。従来の書類提出に代わり、電子的にモデルを提出するペーパーレス化が導入され、現場への立ち入りを最小限に抑える遠隔臨場(リモート検査)の実証も進んでいます。これにより、施工管理業務の効率化や人手不足への対応が期待されています。
こうした取り組みは民間工事にも徐々に波及しつつあり、一部ゼネコンでは施工段階でもBIMが活用できるよう、対応マニュアルや専任チームの整備が進められています。今後は、地方自治体や中小企業にも波及することが見込まれ、制度対応としてのBIM活用が現場実務に直結するフェーズに入ってきました。
補助金で後押し!建築GX・DX推進事業とは
2024年度まで実施されていた「建築BIM加速化事業」は、2025年度から「建築GX・DX推進事業」へと刷新され、補助対象の拡充と継続的なBIM導入支援が図られています【3】。予算規模は2025年度予算として約65億円が計上予定で、設計・施工・維持管理の各フェーズにおけるBIM活用が対象となっており、中小建設会社や地方自治体も、要件を満たせば申請可能です。このように、単なる設計BIMにとどまらず、施工段階でのBIM活用(=施工BIM)も明確に支援対象に含まれています。
補助金額は、設計業務で上限額3,500万円、施工業務で上限額5,500万円(延べ面積などの条件あり)が支給される枠組みとなっています【4】。申請には「BIM活用計画書」の提出や、IFC形式でのデータ連携を含む導入方針の明記が求められます。対象者には中堅・中小企業も含まれており、業界全体でのBIM普及を後押しする制度設計となっています。
実務では、設備設計や数量算出、BIM図面審査の自動化環境整備などへの活用が見込まれています。申請は例年春頃開始のため、年度内の計画策定が重要です。
詳細や最新要項は、国土交通省の公式サイトをご確認ください【3】。
「i-Construction 2.0」が描く建設業DXの未来
国土交通省は、建設業の長期的な変革を目指す方針として「i-Construction 2.0」を策定しました【5】。2040年までに生産性を1.5倍、省人化を30%実現するという目標を掲げ、これまでのICT施工やCIM導入に加え、より包括的なデジタル活用を前提とした構想が提示されています。
この中でBIM/CIMは中核技術として明示されており、3Dモデルを活用した設計・施工・維持管理の統合管理、さらにはデジタルツイン(現場の3D再現モデル)との連動による進捗・安全管理のリアルタイム把握なども検討対象となっています【6】。現場の可視化・省力化・予測管理といった領域での応用が期待されています。
これにより、施工現場では紙・口頭に依存した管理から、統合データ基盤によるプロセス制御への移行が求められます。ゼネコン各社にとっては、自社のDXロードマップ策定や技術導入ステップの再検討が重要になるでしょう。
2026年に始まるBIM図面審査とは
国土交通省は、建築確認手続きのデジタル化の一環として、2026年春を目途に一部地域・特定用途から段階的に「BIM図面審査制度」の運用開始を予定されています【7】。従来の2D図面による紙・PDFでの審査から、BIMモデル(3Dデータ)を基にした審査への移行が検討されており、設計・確認業務の効率化や精度向上が期待されています。
この制度は、初年度は一部地域・特定用途の建築物に限定して段階的に導入され、順次拡大される見込みです。将来的には、2029年までに全国的な義務化を目指して調整中とされており【8】、大規模な民間建築物も対象となる可能性があります。具体的な対象範囲やスケジュールは、今後の検討結果によって変動する可能性があるため、最新の動向を継続的に確認する必要があります。
このBIM図面審査の開始は、建築確認手続きだけでなく、施工現場の進め方そのものに影響する制度転換です。
BIMモデル起点での審査が進めば、そのまま施工フェーズでも数量算出・工程確認・安全管理にモデルを使うことが一般的になると想定されます。
2026年春まで約1年の準備期間を活用し、BIMモデルの構築・提出体制を整えることが、将来の制度対応に向けた鍵となるでしょう。
現場単位で活用できる支援制度
BIMの普及においては、現場単位での活用もいま、業界全体の生産性向上に欠かせない重要なテーマとなっています特に施工の現場で役立つ「施工BIM」は、作業の効率化や段取りの精度向上に直結するツールです。
しかし「導入には費用も手間もかかるのでは?」と不安を感じる方も多いかもしれません。
そこで注目したいのが先ほどもご紹介した、国土交通省の「建築GX・DX推進事業」です。
国土交通省の「建築GX・DX推進事業」では、BIMモデルの作成支援や、ソフト・講習会費用の補助が盛り込まれており【3】、導入を後押しする仕組みが整っています。設計では上限額3,500万円、工事では上限額5,500万円が補助対象となり、一部費用の自己負担でBIM導入を進めることが可能です。
また、東京都・大阪府などでは、自治体独自の支援制度も存在し【9】、国の補助と併用可能なケースもあります。市区町村単位での設備導入補助や、講習費用支援など、現場規模での導入を後押しする制度も整いつつあります。
導入の具体的な手順としては、国土交通省が発行する「BIM活用導入ガイドライン」などを活用し【10】、段階的なステップを踏むことが推奨されます。自社に専門人材がいない場合でも、BIMコンサルや地域の技術支援機関を活用すれば、スムーズに対応可能です。まずは「できる範囲から始める」意識が導入の第一歩となります。
まとめ|制度理解が施工BIM導入成功の第一歩
本記事のポイント振り返り
本記事では、国土交通省が推進する施工BIM制度について以下の内容を解説しました:
- 制度の現状: 2023年度から多くの公共工事でBIM/CIM原則適用が進行中
- 補助金制度: 建築GX・DX推進事業で上限額5,500万円(条件あり)の支援
- 長期構想: i-Construction 2.0により2040年までに生産性1.5倍を目標
- 図面審査: 2026年春から段階的にBIM図面審査制度を開始予定
- 対応の重要性: 将来の義務化可能性に備えた準備の必要性
今後の展望
これらの制度は単なる技術導入ではなく、将来的な業界標準の前提となる可能性が高く、ゼネコン・中小企業を問わず対応が求められます。制度動向を継続的に把握し、自社に適した段階的な導入ステップを計画することが重要です。
次のステップ
施工BIMは建設業界のデジタル化を支える中核技術です。まずは国や自治体の支援制度を活用しながら、講習やモデル作成など手の届く範囲から着手し、制度を味方につけた戦略的な導入を進めることで、工程の可視化やミスの削減、業務の属人化防止など、現場の生産性向上につなげることができます。
施工BIM導入にお悩みの方へ
制度の複雑化や社内リソースの制約により、施工BIM導入に踏み出せない企業様も少なくありません。
BuildAppでは、施工プロセスにおける業務・現場の「不」を解消するサービス・アプリケーションを提供しています。お気軽にご相談ください。

施工BIM活用により、「施工計画の省力化」と「適切な建材管理で管理コスト減」による手配の最適化を実現します。
出典一覧
【1】 国土交通省「BIM/CIMの進め方について 令和7年2月」
https://www.mlit.go.jp/tec/content/001867343.pdf
【2】 国土交通省「遠隔臨場による工事検査に関する実施要領(案) 令和6年 3 月」
https://www.mlit.go.jp/tec/content/001736204.pdf
【3】 国土交通省「建築GX・DX推進事業について」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000201.html
【4】建築GX・DX推進事業(CAD Japan.com)
https://office-akasaki.com/blog/entry-225.html
【5】 国土交通省「「i-Construction 2.0」を策定しました~建設現場のオートメーション化による生産性向上(省人化)~」
https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_001085.html
【6】 国土交通省「i-Construction 2.0~建設現場のオートメーション化に向けて~」
https://www.mlit.go.jp/tec/content/001741646.pdf
【7】 BIM図面審査制度について(オートデスク株式会社)
https://bim-design.com/event/ondemand/bim-drawing-review/
【8】 BIM図面審査制度解説(建築設計ナビ)
https://sekkei-navi.jp/kenchiku/
【9】 東京都「先導的都市づくりプロジェクト(BIM活用支援)」
https://shintosei.metro.tokyo.lg.jp/leading-project/leading-project-70/
【10】 国土交通省「BIM/CIM 活用ガイドライン(案) 令和 4 年 3 月」
https://www.mlit.go.jp/tec/content/001472848.pdf





