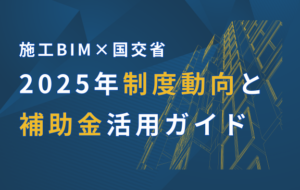現場に潜む「見えないロス」とは?──内装工事のBIM活用による改善アプローチ

【目次】
現場に潜む「見えないロス」とは?
施工現場における非効率の多くは、日々の業務の中に”見えない形”で存在しています。
たとえば、内装工事で発生する廃材、資材の揚重(搬入・移動)にかかる時間、EV(エレベーター)の長時間占有などは、単体で見ればささやかなロスに見えても、積み重なることで現場全体の工程やコストに大きな影響を及ぼします。
建設現場では、石膏ボードの端材や不適合品が廃材として発生する傾向があります。さらに、国交省資料や現場ヒアリングをもとにした一部推計では、一部の現場では、LGS(軽量鉄骨下地材)のカットロスが発生する傾向が確認されています。
また、資材搬入に伴うエレベーターの長時間利用が、作業待機やコスト増加を引き起こす要因として認識されています。とくに多層階の建築物や夜間作業が絡む工程では、他業者との搬入調整が発生し、待機時間やリース費用の追加など、見えづらいコストが連鎖的に発生します。
これらの”見えないロス”は、現場担当者の目には映っていても、工程管理表や原価管理シート上では明確に把握されにくく、結果として後工程や他工種にまで影響が及ぶ構造を持っています。とりわけ「誰が・どこで・どれだけ」無駄を生んでいるかが属人的になりやすく、全体最適を阻む要因となっています。
現場で起きている問題の多くは、資材や工程の計画精度に起因する”段取りのロス”です。そこにこそBIMを活用した情報の事前共有と可視化の可能性があるのです。
揚重・再手配・資材計画…ムダが連鎖する構造
内装工事において、「資材を適切な場所・タイミングで届ける」という一見単純な作業が、実は多くのムダを生み出す起点になっていることがあります。特に揚重作業と資材の再手配は、現場全体の工程や人員配置に連鎖的な影響を与えるため、見過ごせない構造的課題といえます。
例えば、設計図と現場状況とのわずかなズレによって資材の割付位置が変わり、現場での加工や再カットが必要になると、それに合わせて資材の再手配が発生します。一部の実証現場では、一部現場では、資材の再手配や段取り変更により工程へ影響が出るケースも報告されています。その結果、納品スケジュールが後ろ倒しとなり、揚重計画も組み直さざるを得なくなります。
さらに、揚重作業そのものも、建築現場の生産性を左右する大きな要素です。搬入のタイミングが予定通りに進まないことで、夜間対応やリース期間の延長などにより、追加コストが発生するケースもあります。また、EVを長時間占有することで、他業者の作業が制限され、作業エリアの逼迫や工程の押し込みにつながります。
こうしたムダは一つひとつが小さく見えても、全体としては大きな生産性の低下と負荷要因になっていきます。そして多くの場合、その起点は「資材計画の曖昧さ」や「情報共有不足」にあります。
図面の読み取りミス、数量の過不足、揚重タイミングのズレ
──すべてが現場にとっての”段取りのズレ”であり、これらは放置すれば次の工程へと確実に波及していきます。
BuildApp 内装 建材数量・手配サービスでは、こうしたムダの連鎖を防ぐために、資材情報の一元管理と事前可視化のアプローチを提案しています。次章では、その具体的な解決策として「拾い出し精度」を軸にした取り組みを紹介します。
「拾い出し精度」が変える、内装工事の未来
内装工事における資材手配の正確さは、工期やコストに直結します。しかし現場では、手作業による拾い出しが主流であり、設計図面の読み取りやExcel入力の属人性に頼っているケースが多く見られます。この状況は、算出ミスや数量の過不足、手戻りの原因となり、結果としてロスの温床となってきました。
BuildApp 内装 建材数量・手配サービスでは、生産設計BIMモデルをもとに資材数量を拾い出す機能が搭載されています。これにより、算出の精度が大幅に向上し、現場の手作業に依存しないオペレーションが実現できます。 石膏ボードやLGSの拾い出しの精度を向上させ、現場で発生する廃材量削減に繋がります。
さらに、軽量鉄骨(LGS)などの下地材についても、拾い出しの自動化によって部材の過不足が事前に把握できるようになり、再手配や現場加工の手間が大幅に軽減されます。これは、現場での作業をより定量的に、かつ再現性あるものに変えていく第一歩となります。
また、BuildApp 内装 建材数量・手配サービスでは拾い出し結果を帳票化し、ブラウザ上で表示することができます。これにより、「どこで何が必要か」が視覚的に明確になり、所長や番頭・職人への説明・確認作業もスムーズになります。属人的に作成された紙の図面だけでは伝わりづらかった情報も一定のルールに基づき標準化され、理解が促進されやすくなるのです。
こうした「拾い出し精度」の向上は、単なる業務の効率化ではなく、現場における判断と段取りの質そのものを変える可能性を秘めています。
BuildApp 内装 建材数量・手配サービスという選択肢
──現場でBIMが活きる瞬間
拾い出し精度の向上は、現場業務の合理化に直結します。では、その精度を実務にどう活かすか。そこで登場するのが「BuildApp 内装 建材数量・手配サービス」です。
BuildApp 内装 建材数量・手配サービスは、生産設計BIMモデルから割付方針図や間配り計画表を自動出力することで、資材搬入や作業段取りの効率化を支援します。たとえば、EV(エレベーター)の占有時間や、揚重作業のタイミングをあらかじめ調整することで、他工種とのバッティングや作業エリアの逼迫といった問題を未然に防ぐことができます。
また、BuildApp 内装 建材数量・手配サービスかから出力された図面や計画表は、現場内のルート設計や作業配置のベース資料としても活用可能です。「どの部材を、どの階層の、どの位置に、いつ運ぶか」といった段取りを視覚的に共有できるため、現場所長と協力業者間の打ち合わせも短時間で済ませることができます。
操作はシンプルで、初期研修を受けなくても基本的な活用が可能です。自社開発や全社展開を前提としない、現場主導のBIM導入が実現できます。
BuildAppは、ツールとしての機能だけでなく、「現場での実装しやすさ」を軸に設計されています。それは、BIMという仕組みが「使える」ことではじめて、建設現場に価値をもたらすと捉えているからです。
まとめ──見えないロスを、見える改善へ
内装工事の現場には、図面のわずかなズレや段取りの組み直しによる「見えないロス」が潜んでいます。それらは日々の作業に埋もれがちですが、資材の廃棄や揚重のやり直し、EVの長時間占有といった形で、確実にコストと時間を圧迫しています。
本稿では、こうしたロスがどのように発生し、連鎖し、現場全体に波及していくかを明らかにしてきました。そのうえで、精度の高い拾い出しや段取りの「見える化」によって、改善の余地が大きく残されていることをご紹介しました。
BuildApp 内装 建材数量・手配サービスは、こうしたロスの構造を前提に、段階的かつ実務的な解決策を提供します。初期研修不要、1案件からの導入が可能で、「まずは拾い出しから」「1現場だけで試してみる」といった柔軟な導入が可能です。
現場での実装を通じて、見えないロスを見える改善に変えていく
──それが現場起点のDXが目指す方向性です。

施工BIM活用により、「施工計画の省力化」と「適切な建材管理で管理コスト減」による手配の最適化を実現します。
出典一覧(本記事は以下の公的機関資料を参考に作成しています)
・国土交通省「建築BIM加速化事業について」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/bim.html
・国土交通省「建築BIM加速化事業の代表事業者の登録を開始します」https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000954.html
・日建連「施工BIMのすすめ」
https://www.nikkenren.com/kenchiku/bim_susume/index.html
・国土交通省「建築BIM推進会議」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/kenchikuBIMsuishinkaigi.html